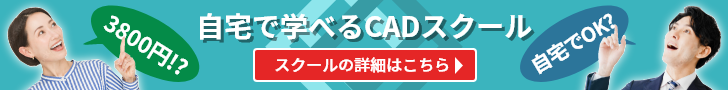はじめに
近年、建設業界では「BIM(ビム)」という言葉を耳にする機会が増えています。BIMは、設計から施工、維持管理までを支える新しい仕組みであり、建設のあり方を大きく変える力を持っています。本記事では、BIMとは何か、その基本からメリット、課題、将来展望までをわかりやすく解説します。
BIMってなに?まずは基本を知ろう
BIMとは「Building Information Modeling(ビルディング・インフォメーション・モデリング)」の略で、建物を作るときに使う3D(立体)モデルと、その中に含まれるさまざまな情報をまとめて管理する方法です。
たとえば、オフィスビルを建てる場合、設計者・施工者・利用者など多くの人が関わります。BIMを使うことで、全員が同じ3Dモデルを見ながら、ドアの位置や材料の種類といった情報をリアルタイムで確認・共有できるのです。
日本では「3Dの見た目+材料などの情報」が重視される傾向にありますが、海外では「情報の流れそのものの管理」を中心とした考え方が一般的です。つまり、BIMは単なるツールではなく、建築プロジェクト全体の進め方に関わる概念でもあります。
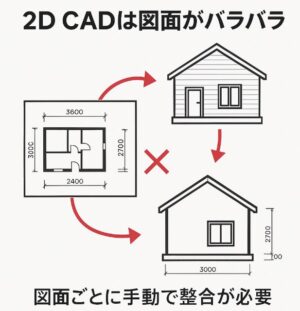

↓ BINM場合は
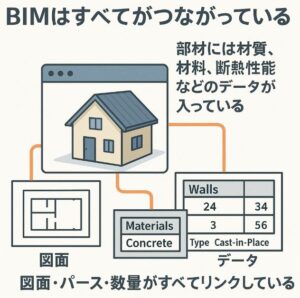 ⇒
⇒ 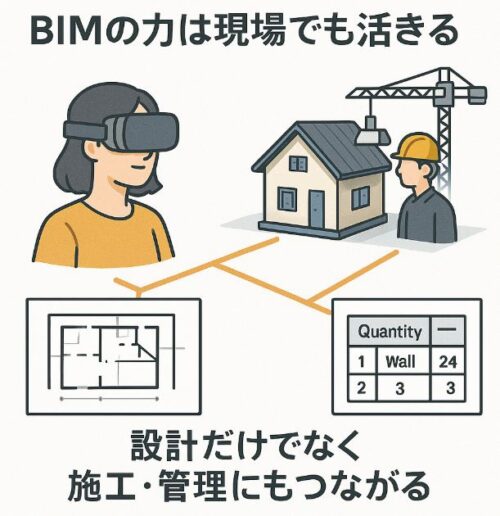
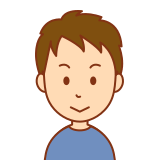
BIMは部材一つ一つに「材質(仕上げ素材の情報)」、マテリアル(材料のデータ、断熱性能等)がすべてはいっています。建物全体の断熱性の計算などもできます。
何より便利なのは変更の際、モデリングでも図面上で構いませんが、1か所修正すれば平面図や断面図、展開図、モデリングまですべて一括で直ります。
建設業界ではありがちな、修正すると「設計図の平面図と展開図では寸法が違う、どっちが正しいの」とか多々ありますよね。
BIMで描いた図面ではそういったことは絶対に起こりません。良いですよね!
BIMを使うとどんな良いことがあるの?
BIMを導入することで、以下のような多くのメリットが得られます:
-
工事前にミスや衝突(干渉)を発見できる
-
設計者・施工者・発注者間の情報共有がスムーズになる
-
材料の無駄やコストの削減につながる
-
工期の短縮とスケジュールの可視化が可能
-
完成イメージを3Dで共有し、合意形成を早められる
たとえば、電気ケーブルや配管が構造部材とぶつかるといった問題も、BIMなら事前にモデル上で確認・修正が可能です。また、使用後のユーザーも、スイッチの配置や室内の動線などを事前に把握できるため、より使いやすい空間が実現します。
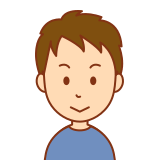
下のパースは鉄骨、電気・機械設備のデータを統合したものです。
すべて可視化され、干渉チェックが簡単に行えます。
2Dでは絶対に無理!
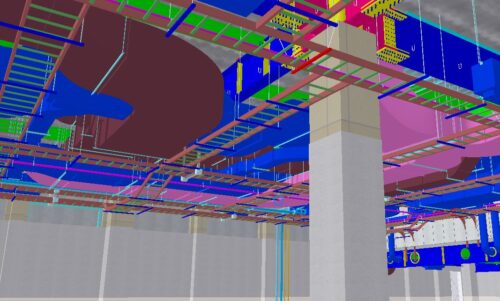
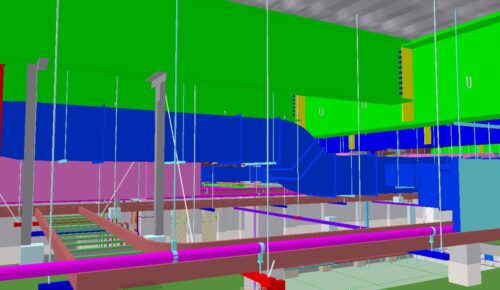
BIMを導入する際の課題
便利なBIMですが、導入には以下のようなハードルがあります:
-
ソフトウェアやハードウェアの初期費用が高い
-
操作習得に時間がかかる
-
既存の業務フローを見直す必要がある
-
ソフト間の互換性の問題
-
情報漏洩などセキュリティ対策も必要
特に中小企業では人手や予算の制限があり、導入が難しいこともあります。また、BIMを動かすには高性能なPC環境も求められるため、機材の整備も課題となります。
主なBIMソフトの種類と特徴
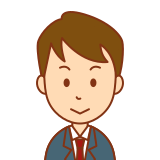
あなたの専門分野は何ですか?
国内でよく使われているBIMソフトウェアの例は以下の通りです:
-
Revit(レビット):建築・構造・設備など多機能に対応
-
Archicad(アーキキャド):デザイン性に優れ、建築家に人気
-
GLOOBE(グローブ):日本の法規に強く、使いやすい国産ソフト
-
Vectorworks(ベクターワークス):2Dと3Dを併用しやすい
-
Rebro(レブロ):設備設計に特化し、精度が高い
用途に応じて最適なソフトを選ぶことが成功のカギです。
日本でのBIMの普及状況と今後
大手ゼネコンや設計事務所ではすでにBIMが導入されており、都市部を中心に普及が進んでいます。ただし、中小企業ではコストや人材面のハードルにより、導入が進んでいないのが現状です。
そこで、国土交通省は「建築BIM加速化事業」をはじめとした補助金制度を設け、BIMの導入支援を行っています。今後は公共事業においてもBIMが標準化され、学校・病院・庁舎などへの応用も期待されています。
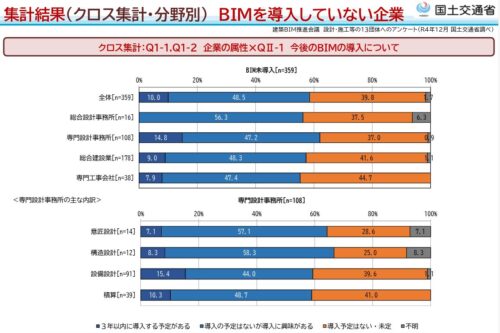
建築BIM推進会議設計・施工等の13団体へのアンケート(R4年12月国土交通省調べ)
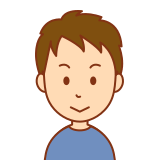
ちょっと古い資料ですが導入状況の資料です。
下のサイトはBIMの活用状況を調査した国交省の資料です。参考にして下さい。
建築分野におけるBIMの活用・普及状況の実態調査<概要>(令和6年度)
BIMと連携する最新テクノロジー
BIMは他の先端技術と組み合わせることで、さらに大きな効果を発揮します。
-
AI(人工知能):設計自動化、エラー検出、最適化提案
-
VR/AR(仮想・拡張現実):仮想空間で設計確認や施工支援
-
クラウド:どこからでもアクセスでき、共同作業がスムーズに
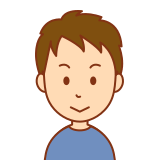
特にVR体験は楽しいし、まだできていない建物の中を歩けるので、既に竣工してしまった感覚になります。お施主さんもイメージ共有されて、竣工してから「イメージと違う直して!」なんてことはなくなります。
これらを活用することで、施工の効率化だけでなく、維持管理や防災の分野でも新たな価値が生まれます。
BIMを学ぶための方法
BIMを学ぶには、以下のような方法があります:
-
初心者向けの書籍で基礎を学ぶ
-
メーカー主催のセミナーやオンライン講座に参加する
- YouTubeの動画講座、Google検索を活用する
※YouTube講座紹介:Archicad Magic ONLINE– Vol.1 第1回 →Vol2.3もあります
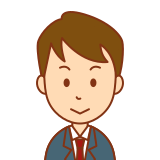
私はほぼ、YouTubeとGoogle検索のみの独学で学びました。
会社ですでに習得している方がいれば教えてもらうのが1番です
近年では無料の学習教材も増えており、独学で始める人も多くなっています。また、大学や専門学校でもBIMを取り扱う授業が増えており、実務と結びついた教育環境が整いつつあります。
まとめ:BIMは建設業の未来を変える技術
BIMは、建物の「設計・施工・維持管理」に関わるあらゆる情報を一元化し、関係者全員で共有・活用できる強力なツールです。導入には課題もありますが、そのメリットは非常に大きく、今後の建設業を支える中核技術になると期待されています。
BIMを理解し、実践できる人材がこれからますます求められる中で、一歩踏み出すことが未来のチャンスにつながるでしょう。