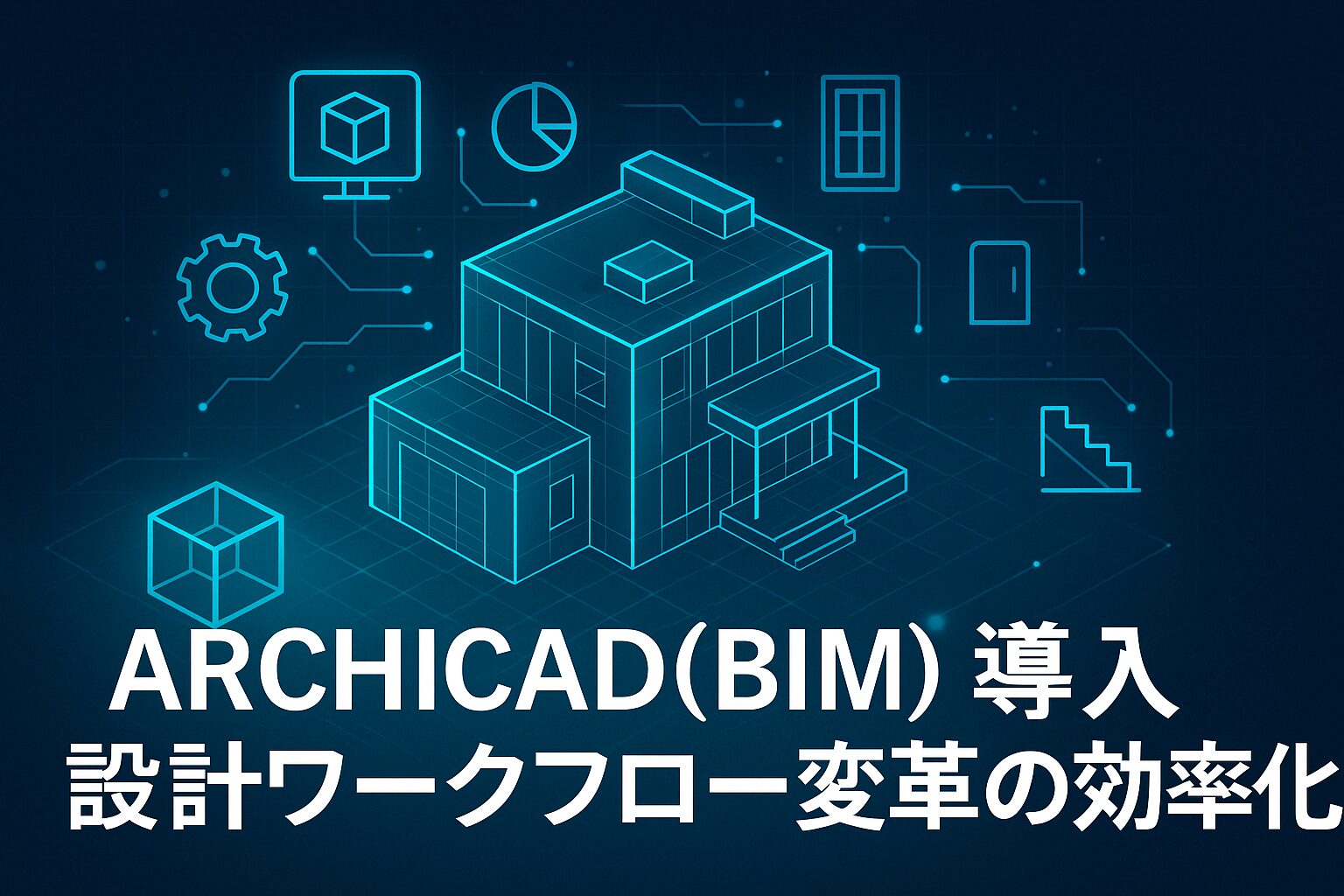建築設計の分野では、近年BIM(Building Information Modeling)の重要性が急速に高まっています。図面だけでなく情報そのものを一元的に扱えるBIMは、これからの設計プロセスに欠かせない技術です。
私はゼネコンの建築工事部に所属しており、設計部や現場をサポートする立場として2019年にARCHICADを導入しました。実務の中で試行錯誤しながらその機能を深く理解してきた経験を、本記事で具体的な事例を交えてご紹介します。
ARCHICAD導入の背景と理由
設計ミスと業務負担の課題
在宅勤務で設計業務を進める中、従来の2D図面では「図面の整合性ミス」や「変更反映の抜け」がどうしても発生していました。
特に、間取りや開口部を変更した際に、立面や断面への反映を手作業で行う必要があり、図面全体の整合性を取るだけで何時間も費やしていたのが現実です。
実際、以前の案件では断面図の建具サイズが古いまま残っていて、現場からクレームを受けたこともあります。作業者が私一人なので、見落とし=責任問題になってしまいます。
こうした状況を改善しようと考えたのが、BIM(Building Information Modeling)の導入でした。
採用理由(UI、レイヤー、視覚化)
複数のBIMソフトを試した中で、最終的に選んだのが「ARCHICAD」でした。理由はシンプルで、**“一人で作業を完結させるのに必要な機能が最も揃っていた”**からです。
まず、直感的なユーザーインターフェース(UI)が秀逸で、2Dと3Dの連動表示により視覚的に図面を確認・修正できる点が非常に大きな強みです。
また、レイヤー管理が柔軟で、用途ごとの図面整理やテンプレート化がしやすく、図面の出力効率も格段に上がりました。
最初は戸惑いましたが、1週間も触れば「これなら現場も自分も助かる」と思える操作性でした。特に3Dで“設計意図がそのまま形になる”瞬間は、設計者としての満足度も高く感じました。
まとめ:ARCHICADの採用を決断した主な理由は次の3点です。
- 建築意匠に特化した直感的なUIと豊富なオブジェクトライブラリ
- レイヤーという概念に基づく、モデリングの作成
-
初期段階からモデルによる迅速な視覚化を可能にする「デザイン流動性」
これらは、設計プロセス全体の見通しや精度を高める上で大きな要因となりました。
独学でスタートしたBIMの習得プロセス
社内でARCHICADを導入したのは私が初めてだったため、導入初期は完全に独学で学びました。YouTube動画やブログ記事、Graphisoftの公式ドキュメントを活用しながら、BIMの基礎から操作まで段階的に理解を深めました。
最初の取り組みは、実際に進行中だったプロジェクトの設計図をベースに、構造、外装、仕上げ、外構までモデリングしていく作業でした。3D化によって、各構成要素の理解が深まり、単なる図面作成では得られない設計上の問題点も浮かび上がりました。
ARCHICADが変えた日々の業務フロー
設計変更の反映スピード
ARCHICADを使い始めてまず驚いたのが、設計変更の速さです。
従来の2D図面では、たとえば間取りを変えたら、平面図・断面図・立面図などすべて手動で修正する必要があり、少しの変更でも何時間もかかっていました。
しかし、ARCHICADでは3Dモデルを修正すれば、関連する図面がすべて連動して更新されるため、変更にかかる時間が激減。
たとえば、開口部の位置を変えるだけでも、関係する図面・スケジュール表が瞬時に反映され、確認ミスも大きく減りました。
図面変更を夜に対応しても、翌朝には反映図を提出できる──今ではこのスピード感が当たり前になっています。
テンプレートと作業効率化
もう一つ、実務で非常に役立っているのがテンプレート活用による効率化です。
特に、自宅改修や提案資料作成などで使う図面には、レイヤー構成や表現スタイルに一定のパターンがあります。
ARCHICADでは一度設定したレイヤー・ビュー設定・図面構成をテンプレート化できるため、新規プロジェクトでもゼロからやり直す必要がありません。
この仕組みによって、図面の品質を保ちながら、作業時間を3~4割カットできるようになりました。
実際、今ではテンプレートからスタートするのがルーティンになっていて、「迷わず描ける環境」が整っている感覚があります。
プロジェクトで得た実感と課題
構造・設備の限界と他ソフトとの連携
ARCHICADは非常に優れた建築設計ツールですが、構造設計や設備設計との連携に関しては限界を感じる場面があります。
特に鉄筋や配管ルートなど、構造図・設備図レベルの精度や干渉チェックを求めると、ARCHICAD単体では対応しきれないことが多いです。
そのため、構造についてはPDF図面を別で確認しながら建築モデルと突き合わせる、設備については最初から簡略化して検討レベルに留めるなど、使い分けを意識する運用をしています。
本格的にBIM連携を行うには、Revitなどとのデータ互換やIFCの理解が不可欠で、今後の課題だと感じています。
BIM環境の整備とマニュアル化
ARCHICADを使って設計業務を進める中で実感したのが、**BIMは「環境を整えてからが本番」**だということです。
テンプレート、レイヤー、分類、図面表現などを場当たり的に設定していると、案件ごとにバラつきが出て非効率になります。
そのため、現在は自分なりに標準化テンプレートやマニュアルを整備しながら、作業環境を改善しています。
「この図面にはこのレイヤーセット」「このパースにはこのマテリアル」など、手順を仕組み化することで、頭を使わずに迷わず描ける環境を目指しています。
まだ発展途上ですが、「再現性のあるBIM運用」ができるようになってきた実感があります。
アップデートで進化し続けるARCHICAD
私が導入したのはARCHICAD 23でしたが、その後毎年のバージョンアップで機能は大きく進化しています。
-
ARCHICAD 24:MEPモデラー統合、PARAM-O導入、ダークモード対応
-
ARCHICAD 25:手すり・階段ツール強化、断面図でのテクスチャ表示
-
ARCHICAD 26〜28:設計オプション、距離ガイド、Keynotes、クラウド連携
これらのアップデートによって、設計者の視点に立った操作性や、社外連携・共有のしやすさが飛躍的に向上しました。
BIMを扱うための基本姿勢
BIMを活用する上で重要なのは、「一気に完璧を目指さないこと」です。最初は小規模なプロジェクトや、プレゼン用のモデルからでも十分です。実際に手を動かしながら、自分に合った使い方を見つけるのが近道です。
テンプレートの整備、属性設定のルール化、社内マニュアルの作成など、BIM環境の構築も効率化の鍵となります。チーム全体で知識を共有しながら進めることで、属人化を防ぎ、業務全体の質が高まっていきます。
今後の発信予定
この記事では、ARCHICAD導入の背景や活用経験について主にご紹介しましたが、今後は以下のような内容も随時アップデートしていきます。
-
ARCHICADの機能詳細とおすすめ活用法
-
使用しているPCスペックの紹介
-
ICT技術(ドローン撮影、クラウド共有など)の実務活用事例
-
他ソフト(Rebro、SketchUp、Twinmotionなど)との具体的な連携手法
実務で役立つ情報をリアルにお届けし、同じようにBIM導入を検討している方々の一助となれば幸いです。
おわりに
ARCHICADの導入は、私の建築設計・施工業務を根本から変える大きな転機でした。作業のスピード、正確性、提案力が飛躍的に向上し、クライアントとのコミュニケーションも格段にスムーズになりました。
設計者としての視野が広がったことで、より創造的かつ柔軟に業務へ向き合えるようになり、日々のモチベーションにもつながっています。
BIMやARCHICADの導入に迷っている方がいれば、私の経験が少しでも参考になれば幸いです。今後も進化する技術を柔軟に取り入れながら、より良い設計環境を目指していきたいと思います。