使用環境のはじまり:一般的なノートPCからの挑戦
ARCHICAD導入初期の環境と苦労
私がARCHICADを使い始めたのは2019年10月のことでした。当時使用していたのは、ごく一般的なノートパソコンで、グラフィックボードも搭載されていないものでした。そのため、通常のARCHICADの操作も時間がかかり、特にレンダリング作業には非常に時間がかかり、特に最高画質での出力には12時間以上を要することもありました。帰宅前にレンダリング作成を開始し、一晩レンダリング作業をPCにさせましたが、翌朝出社しても出来上がっていませんでした。
独学で習得したレンダリング技術
当時は、効率的に作業できる環境とは言えませんでしたが、それでも少しずつ操作に慣れながら、試行錯誤を重ねてARCHICADの基本操作からレンダリングの設定に至るまで、独学で知識を深めていきました。失敗も多く、思い通りの表現ができないこともしばしばありましたが、それら一つひとつの失敗が学びに変わり、着実にスキルとして身についていったのです。
その後、業務の効率や品質向上のために会社へ高スペックなPCの導入を提案し、無事に最新のマシンが導入されました。これにより作業スピードが格段に向上し、より高品質なパース作成や設計検討が行えるようになりました。BIMを活用するうえで必要なPCスペックや周辺機器の選定についての情報も、今後は記事や資料として整理し、共有していく予定です。
高品質なパース作成の実例紹介
自宅改修プロジェクトの概要
業務で扱った案件は守秘義務の関係上公開できませんが、2年前に実施した自宅改修工事では、ARCHICADの持つポテンシャルを最大限に活用しました。
自宅の改修は、単なる模様替えや修繕ではなく、在宅勤務を快適に行うための“働く場”の最適化が目的でした。限られたスペースの中で「集中できる環境」「家族との動線の調和」「光の取り込み」を考慮し、設計プランを立案。ARCHICADを活用することで、天井の勾配や収納の位置、デスクスペースの寸法まで詳細にシミュレーションしながら進めました。
パースと動画を使った家族プレゼン
実際に作成したパースやウォークスルー動画を使って、家族に完成イメージをプレゼンしました。紙の図面だけでは伝わりにくい空間の広がりや光の入り方も、3Dパースで表現することで「本当にこの形で大丈夫?」という不安を払拭することができました。
特に妻からは「まるで完成した部屋にいるみたい」と驚かれ、改修内容に納得してもらえたのが印象的でした。
この工事は自宅の改修工事のため、企画、設計、見積もり、施工管理に至るまで、すべての工程を私一人で担当しました。
実際に作成したパース(ARCHICAD レンダリング機能) の紹介
以下に、ARCHICADで作成した自宅改修に関するレンダリングパースをいくつかご紹介します。これらのパースは設計検討だけでなく、家族とのコミュニケーションやイメージ共有のために非常に有効でした。
-
和室の解体とワークスペースの新設:生活と仕事の動線、家具の配置計画を考慮した空間構成。照明の配置や床材の質感、壁面の色味まで具体的に表現。
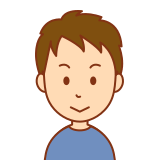
ビフォーアフターのパースだよ、こんな感じです。
【 改修前 平面パース】

【 改修後 平面パース】

【 改修後 断面パース(昼・夜)】


このようなパースは、設計者としてだけでなく、施主として自分の希望を具現化するためにも非常に役立ちました。特に、パースや動画は、完成後の空間イメージを妻に分かりやすく伝えるためのプレゼン資料とし活用しました。
後になって妻からクレームが出ないよう、細部まで丁寧に表現するよう心がけました。どこに何が配置され、どのように動けるのか、どれほどの光が差し込むのかなど、図面だけでは伝えきれない感覚的な情報を視覚化することで、家族との意見のズレを未然に防ぐことができました。
結果的に、こうしたビジュアル資料は家族との円滑な意思共有を支えるツールとなり、設計段階から納得した上で空間づくりを進めることができました。完成後の満足度も非常に高く、「最初にパースを見ていたからイメージ通りだった」と言ってもらえたことは、非常に嬉しい瞬間でした。
「あなたのBIM活用事例もぜひコメントで教えてください!」
「パース制作の具体的な設定方法に関する解説も希望があれば記事化します!」
次回はさらに深掘り!実践的なパーステクを解説予定
今回は、自宅改修という実例を通じて、パース作成とARCHICADによる時短テクの活用をご紹介しました。
今後は、より視覚的に訴求できるパースの工夫や、設定のコツ、さらに効率的な作業環境づくりについても記事化していく予定です。
「どんな設定でこのパースができるの?」「Twinmotionとの違いは?」など気になる点があれば、ぜひコメントやメッセージで教えてください。
