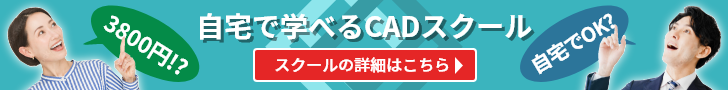自宅リノベーションの実体験をもとに、建築BIMソフト「ARCHICAD」とリアルタイムビジュアライゼーションツール「Twinmotion」の連携がもたらす価値を解説します。空間の魅力を正確かつ直感的に伝える手段として、この2つのツールがどのように活用できるのか、具体的な手法や利点を紹介します。
Twinmotionとは
建築設計のためのリアルタイム3Dビジュアライゼーション
Twinmotionは、Epic Gamesが開発したリアルタイムビジュアライゼーションソフトです。Unreal Engineをベースに構築されており、操作性に優れながらも高品質なビジュアルを簡単に生成できるのが特徴です。建築設計やインテリアデザインなど、空間の提案において圧倒的な表現力を発揮します。
Epic Gamesと建築業界への貢献
Epic Gamesはゲームエンジン「Unreal Engine」の開発元として知られていますが、建築・建設業界への取り組みも強化しており、TwinmotionやDatasmith Exporterといったツールを通じてBIMとの連携を推進しています。
Twinmotionの主な機能と強み
-
マテリアルやライティングのリアルタイム調整
-
季節や時間帯、天候などの環境シミュレーション
-
人物・家具・植栽などの簡単配置
-
静止画、動画、VR対応コンテンツの出力
ARCHICADとTwinmotionの連携による効率化と表現力向上
LiveSyncによるリアルタイム同期
ARCHICADとTwinmotionのLiveSync機能を使えば、設計の変更がTwinmotionに即時反映されます。これにより、建築モデルの編集とビジュアライゼーションを同時並行で進行でき、作業効率が大幅に向上します。
-
書き出しの手間が不要
-
図面と3D表現の整合性が維持できる
意図を直感的に伝えるプレゼン
自宅改修プロジェクトでは、Twinmotionによるビジュアル資料を使って家族に提案を行いました。間取り変更、家具の配置、採光計画など、図面だけでは伝わりづらい要素も、映像を通じて明確に表現できました。
Twinmotionを使った動画プレゼンの実践
Twinmotionで作成した動画では、以下の要素を意識しました:
-
実際の動線に沿ったカメラの動き
-
時間帯ごとの光の変化(朝・昼・夜)
-
目線の高さを意識したリアルな視点
これらの工夫により、提案する空間での生活イメージをリアルに伝えることができ、関係者からも具体的なフィードバックを得ることができました。
Twinmotionが建築プレゼンにもたらすメリット
-
「見せる」ことで設計意図を即座に共有
-
修正や変更点の反映がスピーディー
-
VRや360度ビューによる没入型プレゼンも可能
-
説明資料としての視覚的な信頼性が高まる
結果として、合意形成までの時間が短縮され、提案の説得力も向上します。
参考に自宅改修工事の動画を掲載します。今となってはレベルの低い動画ですが、今はレベルアップしています。
建築以外の分野にも広がる活用範囲
Twinmotionは建築以外にも、さまざまな分野で活用が広がっています:
-
インテリア・商業施設の空間演出
-
展示会ブースやイベントスペースのシミュレーション
-
製品配置・パッケージデザインの検証
-
メタバースやVR空間の開発プロトタイプ
「空間の可視化」が求められるあらゆるシーンで、その性能を発揮します。
ARCHICADユーザーのための応用技術
Datasmith Exporterによる高精度連携
Epic Gamesが提供する「Datasmith Exporter for ARCHICAD」を使用することで、TwinmotionやUnreal Engineとのより高度なデータ連携が可能になります。モデルの階層構造やマテリアル設定をそのまま保持でき、より自由度の高いビジュアライゼーションが実現します。
-
複雑な構造や演出表現にも対応
-
Unreal Engine上での拡張も視野に入れられる
ダイレクトリンクによる共有の簡素化
Twinmotionでは、制作したプロジェクトをブラウザ上で共有できる「ダイレクトリンク」形式のURLを発行可能です。
-
関係者はソフト不要で閲覧可能
-
クラウド上の共有により、修正も即時反映
-
プレゼンやレビュー、確認作業が効率化
まとめ
TwinmotionとARCHICADを連携させることで、設計の可視化とプレゼンテーションの質を大幅に高めることができます。設計者の意図を直感的に伝える力は、合意形成のスピードと確実性を向上させ、関係者全体の満足度を高めます。
特に、設計の意図や空間の価値を「見える化」する手段として、Twinmotionは非常に有効な選択肢です。今後のプロジェクトにおいて、ぜひ実務レベルでの導入を検討してみてください。